まいど、ひろきんです。
「やりたいことがないから公務員になろう」
「安定しているし公務員かな」
と考えている人は市役所で働くイメージを持たれている方が多いと思います。
この記事を読むと、そのぼんやりとした公務員像が具体的になり、あなたの今後の進路を想像できるようになります。
校務員になるというのがどのようなものなのかをリアルに知ることができます。
地方公務員の仕事はこんなにある!

公務員は国家公務員と地方公務員の2つに分かれます。
どちらも自分が希望する職種に沿って行われる「公務員試験」に合格しなければなりません。
市役所で働くイメージが大きいですが、市役所職員は地方公務員の行政職です。
今回は地方公務員の職種についてピックアップしてみました。
地方公務員とは、「住民が安全に生活できるまちづくりに関わる全て」を担います。
例えば治安、教育、文化事業、学校、病院、清掃、ごみ処理などです。
また、「特別職(知事、市町村長、議員など)」と「一般職(特別職以外)」の2つに分かれます。
以下は一般職です。
行政職…まちづくりや地域住民の生活を支える仕事。
配属先は、
- 都道府県県庁
- 市役所…住民課、税務課、福祉課、年金課などさまざまな課に配属される。
戸籍や住民票の手続きなど各種手続き、窓口対応、事務処理を行う。
社会福祉に関する相談対応や支援活動を行う。
- 公立小・中学校…会計や備品管理などの学校事務。
- 警察署内…職員の福利厚生、給与計算、広報などの警察事務。
技術職…「土木」「建築」「電気」「機械」「化学」「林業」「農業」などの分野。理系公務員。
・「土木」…河川や海岸の開発と災害対策、公園、道路など公共の場での整備や管理を担当。
建築物の耐震対策、出先機関の増築・改築など公共物に広く関わる。
・「建築」…公共建築物の耐久性を追求する。浄水場や下水処理場、トンネルなどの工事で
は企画立案から工事監督、メンテナンスを行う。
・「電気」…電光掲示板、街灯など広く保守点検や修繕を行う。災害時における情報通信の企画や改善。電気自動車や工場の省電力機器などの研究や普及にも関わる。
・「機械」…庁舎や空港の空調、エレベーターやエスカレーターの設置などの企画と工事。
自治体内の各種施設管理や実際の技術的部分についての仕事。
・「化学」…学校のプール、浄水所や下水処理場の水質監視、スーパーやデパートの衛生監視。工場や交通では、騒音、悪臭などの確認と管理指導。食中毒やインフルエンザの予防を呼びかける。
・「林業」…林道開発における設計・監督業務。特用林産物や優良苗の安全確保。
・「農業」…自治体内の農業に関連している分野を担当。学校での食育、各種農家への指導や助言、各地方自治体の特産品をアピールし、地域活性化につなげる。
資格免許職…資格や免許が必要な職種。大学で習得。
・「保育士」、「教師」、「管理栄養士」、「栄養士」、「看護師」「薬剤師」「獣医師」「保健師」「栄養士」「司書」(図書館勤務)「学芸員」(美術館や博物館に勤務)など。
公安職…警察官、消防士。
・警察官…国家公務員と地方公務員の両方がある。(皇宮護衛官、都道府県警)
・消防士…試験が上級、中級、初級に分かれており、採用区分に応じて管理職から現場に分かれる。
心理職、福祉職…各種相談所において心理判定などの業務、生活に関する支援を行う。
・心理判定員として心理面接、心理診断、心理学的援助を行う。
・ケースワーカー…高齢や障害による、生活保護に関する相談支援や対応を行う。県立の病院、児童相談所、老人福祉施設、福祉事務所などに勤務。臨床心理士などの資格を持って学校のカウンセラーに従事することも。
このように公務員と言っても多岐にわたります。
これからを考えている人は、様々な職種があるうえでこれからの進路を考えてもらえればと思います。
地方公務員になるには?

地方公務員試験は試験方法が自治体によって異なるので確認が必要ですが、基本的に
- 第一次試験…筆記試験。「教養試験」と「専門試験」がある。
- 第二次試験…面接
の2段階で行われることが多いです。
筆記試験は希望する職種によって内容が異なりますし、試験に学力のレベルを設けているものもあります。
よく見かけるものでややこしいものではこちらです。
都道府県の採用
・地方上級(大学卒業程度)…国家公務員の一般試験と同レベル。自治体の幹部候補生。
・地方中級(短大・専門学校卒業程度)
・地方初級(高校卒業程度)
各市役所の採用
・市役所上級(大学卒業程度)
・市役所中級(短大・専門学校卒業程度)
・地方初級(高校卒業程度)
名前がややこしいですが、これは県に採用されるか市で採用されるかの違いです。
これらはあくまで「試験のレベルの目安」であり、年齢などの条件を満たせば高卒の人が上級試験を受けることも可能です。
どのレベルの試験に合格するかによって、給与や待遇、出世に差が出てきます。
地方公務員と相性の良い学部
「専門試験」では行政職、技術職など希望する職種によって出題される内容が違います。
法学部、経済学部
行政職(市役所勤務など)の筆記試験(専門科目)では
・法律系(憲法、民法、行政法、労働法、刑法、商法など)
・経済系(ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学、経営学、会計学、統計学など)
・行政系(政治学、行政学、社会学など)
の3分野に大きく分けられます。(すべてが出題されるわけではなく、出題科目や選択科目は異なります。)
行政職は、法律や経済と幅広いので、自身の学部と関係がない分野を勉強する必要があります。
理系学部、心理学系
・理系学部は技術職として、それぞれ得意分野のエキスパートとなります。
・心理学系では、心理職・福祉職を目指します。
これらは大学で学んだ専門知識で対応できます。
公務員になって何が学べる?!経験者のリアル

これまで地方公務員の職種となり方を説明しました。
そこで、今度は実際どうなのかについて解説していきます。
事務作業が中心の業務のため、専門的なスキルは付かない。
・文書作成スキル
・PCスキル
・法律を読み書きするスキル
・わかりやすく説明するスキル
・データの入力や窓口での書類発行業務など
・前例にならって業務を進める
・過去の様式の数字を差し替える作業
・副業は禁止されている
つまり慣れれば誰でもできる作業で頭を使わないんですよ。
公務員のデメリット
できる人ほど忙しい部署へ
普通に働いていれば首にならないので、仕事面や人間面で問題がある人は業務が少ない部署に配属される。優秀な人ほど忙しい部署に配属される。
安定で転居がないイメージだが異動あり
約2.3年で他の課への異動があり、それぞれの特殊スキルが身に着く。
上記「行政職」にある通り、事務職は配属先が様々なので転職レベルの部署移動がある可能性も。
良くも悪くも年功序列
基本、上の言うことに従うので「若いうちから成績に見合った給料が欲しい」「自分のやりたいことを発信したい」人には向かない環境。
給料は徐々に上がる。
後悔しないためにやるべきこと
僕の持論ですが「やりたいことがないから」「安定しているから」という理由で公務員を目指すことは悪いことではないと思います。
生活のために働くのはあなたで、その仕事を選ぶ理由に第三者が意見できないと思うからです。
そのために公務員試験の勉強をこなすのは、それはそれですごいことだと思います。
また、仕事をしているうちにやりがいを感じることもあります。
しかし、あとで後悔しない為にもやるべきことがあります。
それは、「あなたの価値観と合っているか?納得しているのか?」ということです。
自分にとっての仕事の考え方

- 仕事は仕事と分け、プライベートが充実していればよい
- 興味のある仕事でないと続かない
- 仕事にやりがいをかんじたい
あなたはどうでしょうか。
「①仕事は仕事と分け、プライベートが充実していればよい」人であれば、仕事は仕事と割り切って何でもできるのかもしれません。
しかし、「②興味のある仕事でないと続かない」と感じる人であれば、公務員の職に興味がないと週5日8時間労働はしんどいと思います。
このように、目先のメリットや「なんとなく良い」というイメージだけで決めてしまうとあなたの価値観と合わなかった時、後に我慢する所が出てきてストレスを感じながら働くことになるのです。
勤務形態に納得できる?
人には「これが好き」「これだけは譲れない!」ということがあると思います。
例えば異動や転勤の有無などです。
事務作業が「専門知識も得られないし自分のためにならない」と思うのか、「仕事だしこんなものだよ」と思うのか。
また、上にも書いたような職業はそれぞれ勤務形態などが異なります。
もしあなたが興味のある職を見つけたなら調べてみて「納得できるか」を考えてみましょう。
世の中には公務員でも民間企業でも辞める人は辞めますので、自身の価値観と合うか、100%条件が合わなくても納得しているかが大事です。
実際に、僕はどっちも辞めて起業しているので、納得できる選択肢を選ぶのが一番だと思います。
まとめ
このように地方公務員というだけでも様々な職があり、試験内容も職や自治体によって異なります。
試験対策はすぐにできるものではないので、早めに対策していきましょう。
一般的に市役所で働くイメージが大きいですが、自分が働くイメージをもって「自分の価値観と合うか・納得できているか」を確認しましょう。




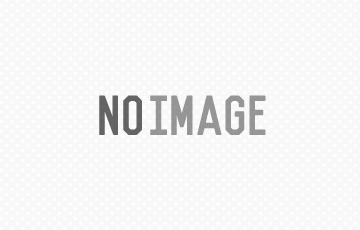





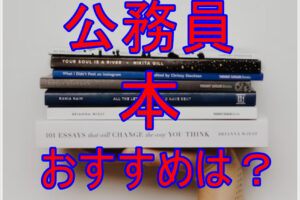
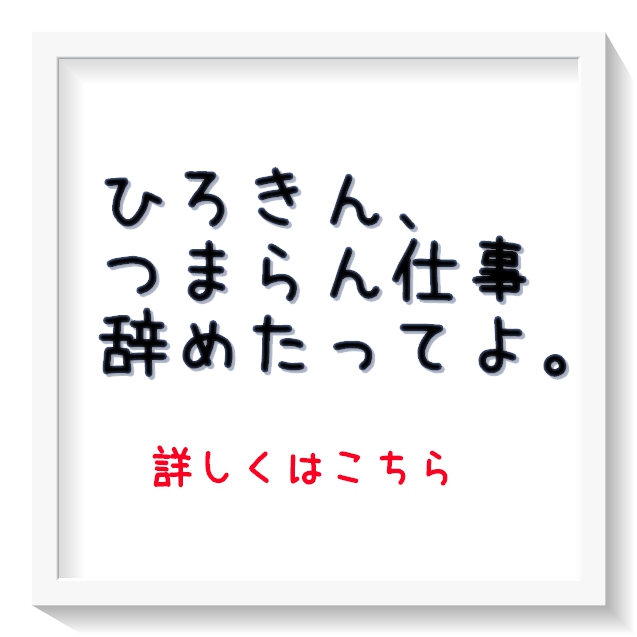




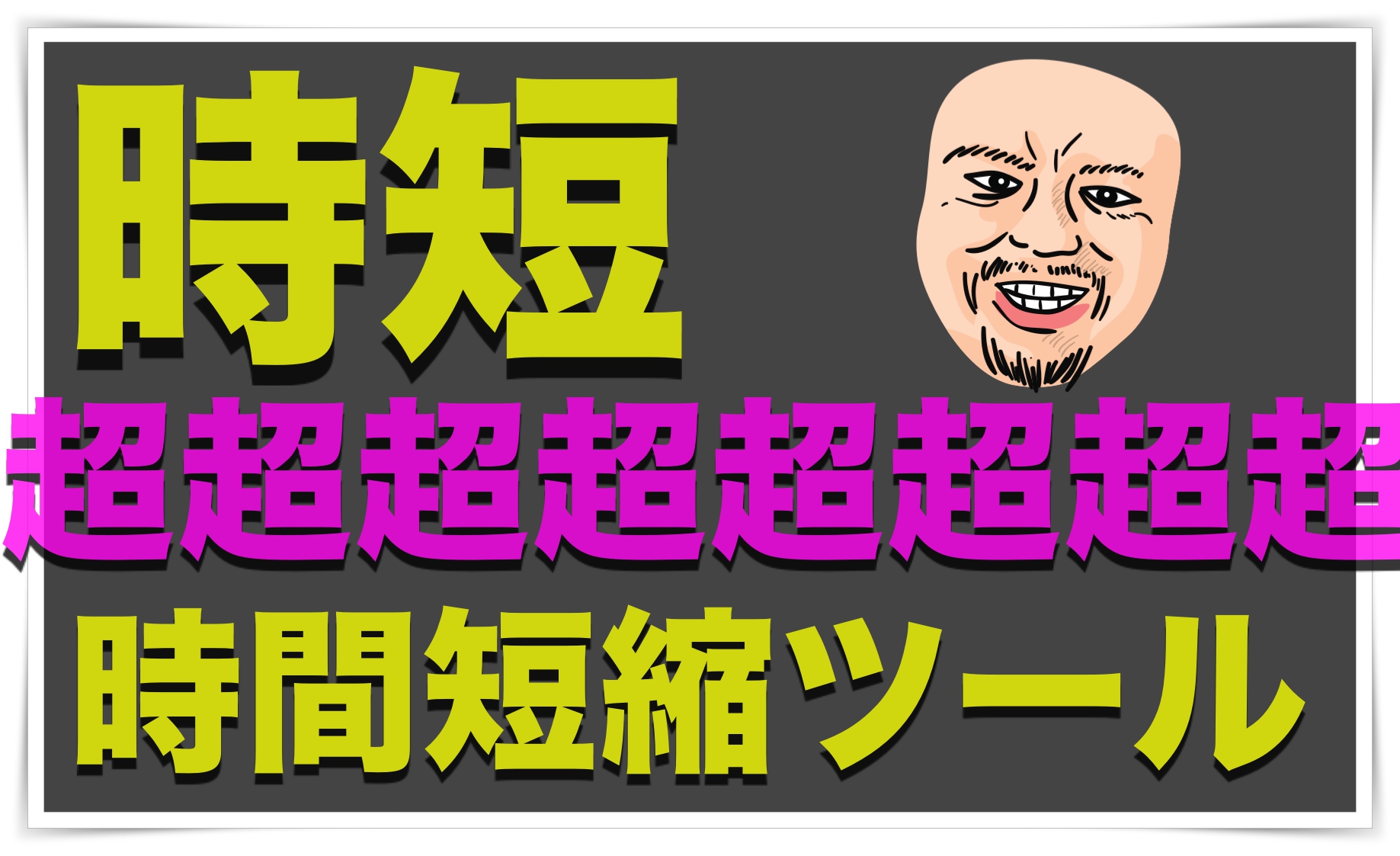


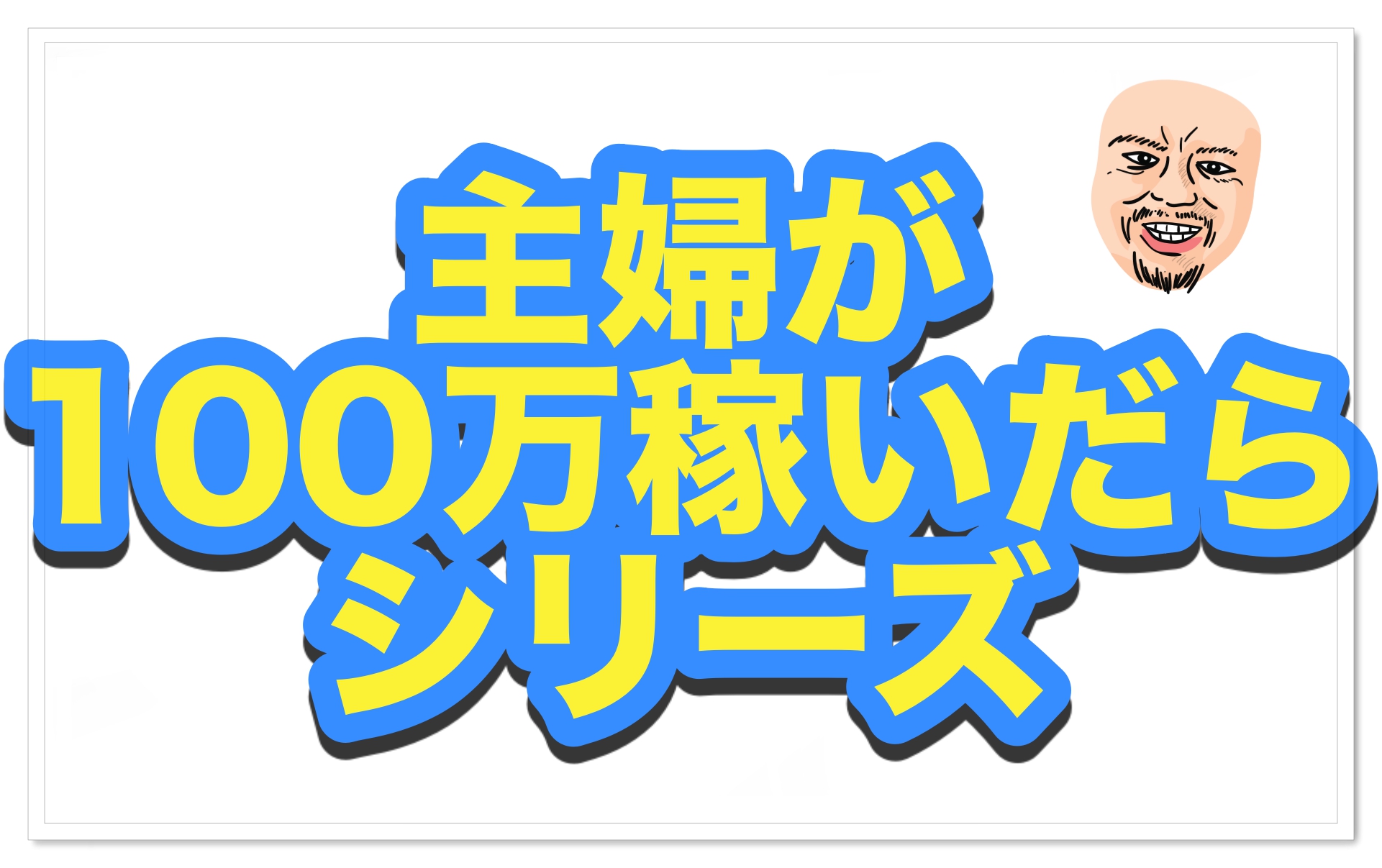
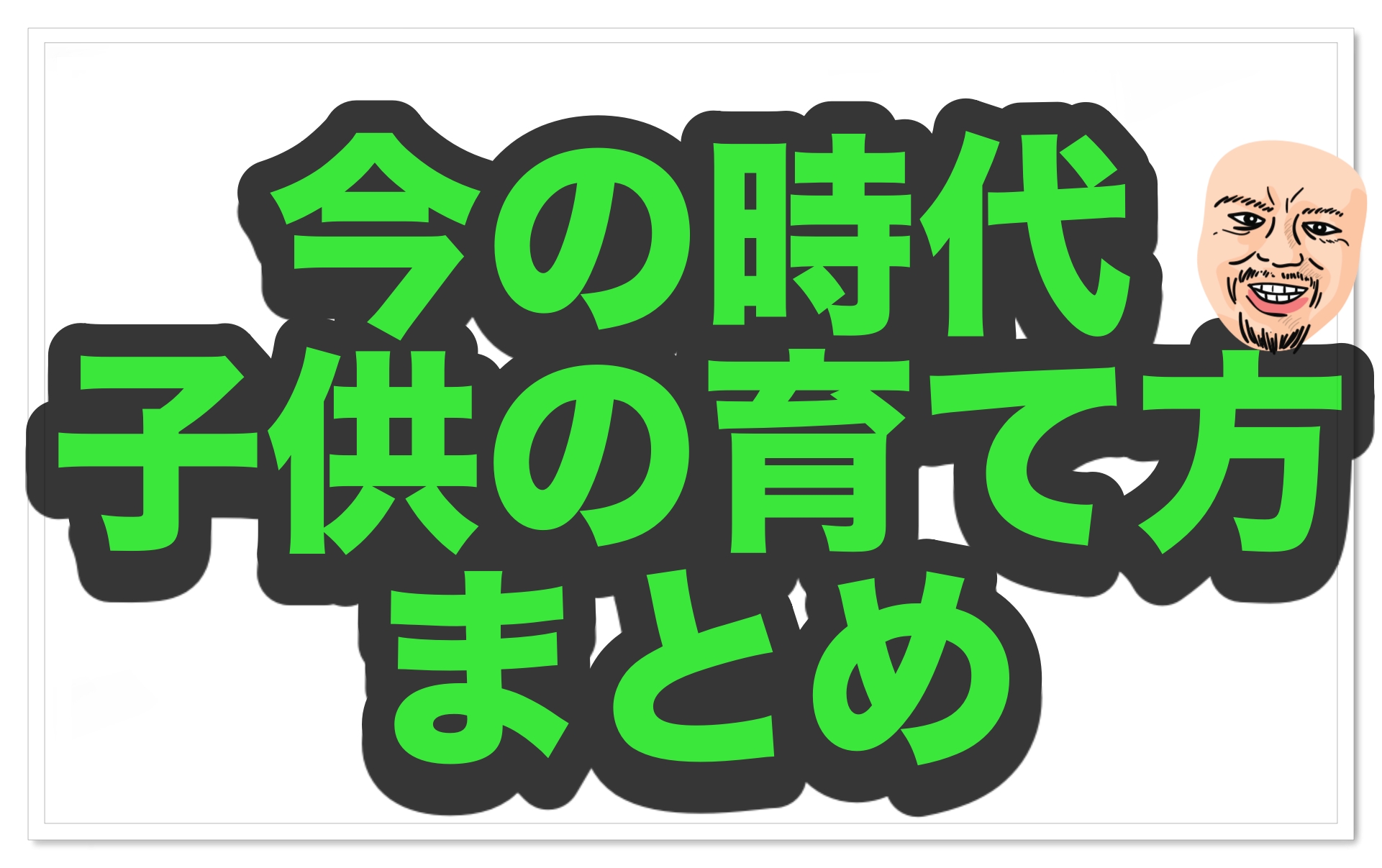

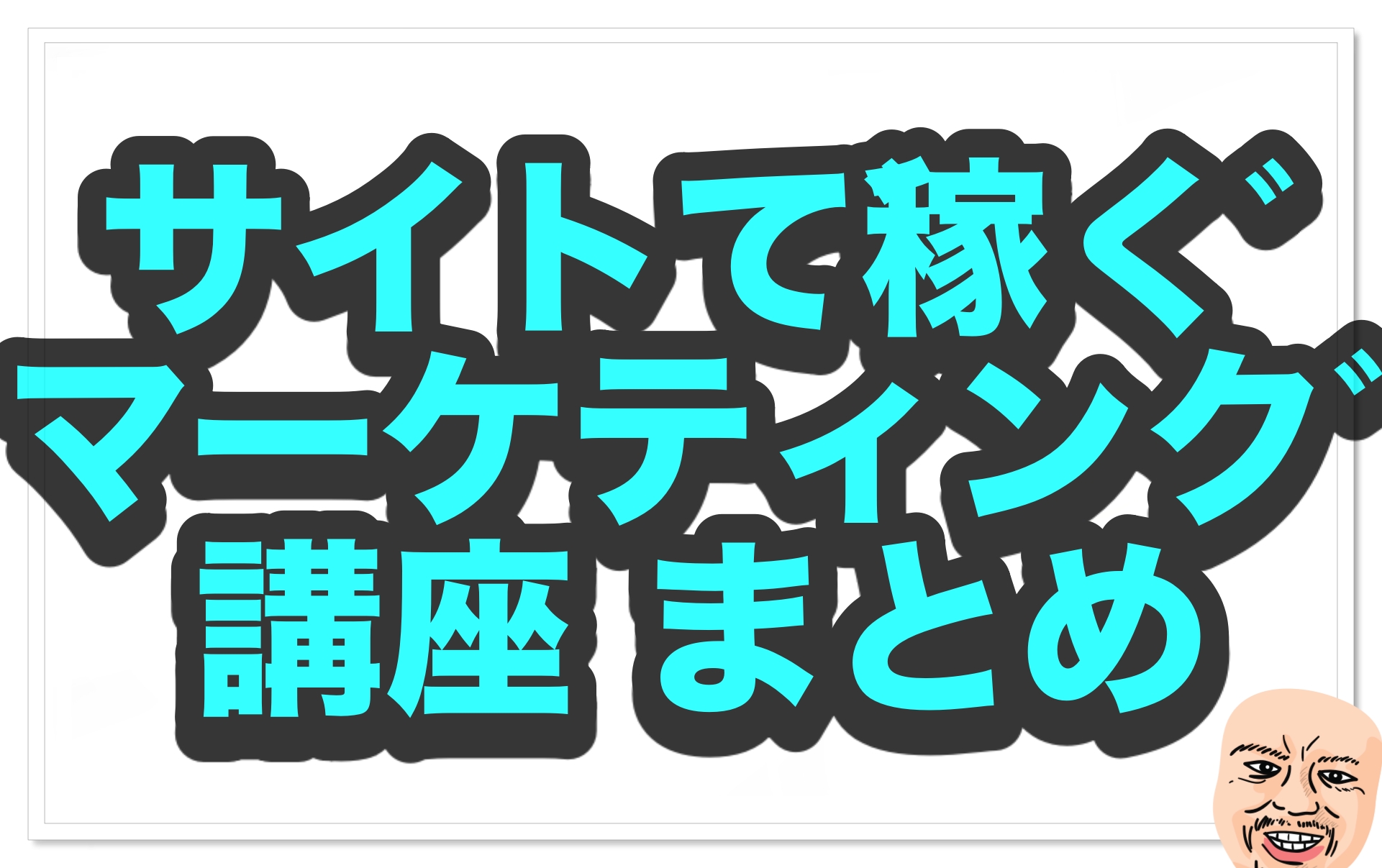

コメントを残す