まいど、ひろきんです。
今日は公務員におすすめの本についてです。
僕は元公務員で、現在は退職しましたが、ずっと、いろんな本をたくさん読んでいます。
本を読むというのは本当におすすめです。
公務員が読むのにおすすめの本は?:公務員の仕事の基本を学ぶのに役立つ本

公務員の仕事に役立つ本を読んで知識を得られれば、仕事がやりやすくなると思います。
知識が増えて作業のスピードが速くなったりミスが少なくなったりするだけでなく、周りから「お、この人は○○(仕事上の何か)について詳しいんやな」とも思ってもらえる可能性が高まります。
声をかけてもらえることが増えれば、先輩や同僚との良い関係も気づきやすいかもしれませんよ。
中でも”基礎”をしっかり学んでおくと、後輩ができた時にも役立ちやすいでしょう。
(ただし、仕事ができすぎる→どんどん自分に仕事がまわってくる→断れないと辛くなる一方、ということもあるのでバランスが必要です…)
どんな部署でも必ず役立つ 公務員の読み書きそろばん [ 林 誠 ]
\新刊!/『どんな部署でも必ず役立つ 公務員の読み書きそろばん』(林 誠 [著]、定価=税込1980円)
総務・企画部門から事業部門まで、どこに異動しても使える基礎・基本スキルについて、「読み書きそろばん」になぞらえてピックアップ!https://t.co/skw7cZhSew pic.twitter.com/xz6I1bz3sH— 株式会社 学陽書房 (@gakuyo_syobo) June 18, 2020
- テクニックだけでなく公務員の心構えも学べた
- 公務員ならではの視点と、社会人の基礎的な視点両方をポイント所をしっかり学ぶことができる
- 「(書類などを)読む」「書く(起案する)」「そろばん(財政)」「話す(コミュニケーション)」「IT(パソコン等)」などについて分かり易く解説しており、丁寧に読み易く書かれていて良い
と言った口コミもあり、高評価な本ですよ。
4月から公務員になる方は、とりあえず「疑問をほどいて失敗をなくす 公務員の仕事の授業」か「どんな部署でも必ず役立つ 公務員の読み書きそろばん」を読むといいと思うよ
— 初心シャ (@tihoujiti12345) February 23, 2021
著者は埼玉県の所沢市役所で財務部長も務めていた林誠氏です。
実際の市役所での成功/失敗体験がもとになっているということですよ。
(林氏は令和4年4月の人事異動により市民医療センター事務部長を務めていらっしゃるようです)
地方公務員の仕事は多岐にわたり、「配属ガチャ」、「異動は転職並み」なんていう人もいます。
思い通りの配属にならず「大丈夫やろか…」と不安になるかもしれません。
そんな時に、この本にはどの部署に配属されても、また、仮に公務員でなくなっても社会人として必要な、基礎的なことが書かれていて、助けになるというわけですね。
また、公務員は異動が”多い”のですが、こういった基礎知識を持っておくと新しい職場や今までと全然違った担当になっても、慣れやすくなるかもしれません。
一方で、
- ある程度公務員生活に慣れてきた人にとっては満足できないかも
- 公務員特有のルールは載っていない
などという声もありますよ。
「公務員としてある程度の年数が経っていても、案外知らないことがあったり確認するのに使える」という声もありますが、もっと知識を深めたい場合は、それぞれの仕事の専門的な本も併せて読んでいく必要があるかもしれませんね。
ちなみに、「公務員の仕事の授業」の著者(共著)の方もこんなツイートをしています。
「どんな部署でも必ず役立つ 公務員の読み書きそろばん」が出たとき、内心「ぎゃあ」と思ったのは内緒だσ(^◇^;)
でも、読んでみたらアプローチの違いから双方補完する感じでした
ぜひ併せて読了を— kei-zu■発売中「公務員の仕事の授業」 (@keizu4080) February 23, 2021
疑問をほどいて失敗をなくす 公務員の仕事の授業 [ 塩浜 克也 ]
「疑問をほどいて失敗をなくす 公務員の仕事の授業」という本では、
- 地方自治体の新採職員が、仕事の基盤となる地方自治制度や地方財務制度、法律の読み方、議会対応等をざっと学ぶのによい
- 新人から中堅まで、役所仕事で迷子にならないための、必修の基礎知識
という口コミもありますよ。
また、
- 転職前や新人研修時には少し難しいかもしれない
- 一年間の業務の流れを知った後(二・三年目)の職員にはとても有益な本
- 指導員になった時にも役立つ
- 中堅になった時の復習にもなりそう
という声もあります。
一度読んで難しくても、改めて読んでみる、というのも良いかもしれませんね。
公務員が読むのにおすすめの本は?:「異動でキツイ…」など、悩みと向き合うための本

公務員はぬるま湯だとか言われますが、状況によってはキツイこともありまよす。中には鬱になって休職する人もいますね。
例えば人間関係や異動の多さが原因でつらい思いをする人もいます。
でも、「みんなも異動しているし…」とか、民間企業の人には「うちはもっと大変やし」なんていわれそうで、なかなか人には相談できずにいるなんていうこともあるかもしれません。
そんな時に、本を読んでみるというのはとてもおすすめです。
もちろん、今の悩みを完全解決してくれるとまでは行かないかもしれません。
しかし、同じ悩みを抱えた人が著者であれば、「自分だけじゃないんだ」と、それだけでも楽になることがあります。
また、それに向き合ったらいいかというヒントも得られたり、自分だったらこうする、とアイディアがわいてくるかもしれませんよ。
公務員が人事異動に悩んだら読む本 [ 岡田 淳志 ]
公務員の最近の離職増や採用難。
人事が全くのブラックボックスで、
・キャリア形成に主体性が持てない
・異動の理由や意図の説明がない 等々
今時こうした組織は職業選択で避けられてしまう。ここを変えずに公務員の魅力をいくらPRしても底の抜けたバケツに水を注ぐのと一緒。
— さる@現役市役所職員の日常 (@karinokoumuin) November 20, 2022
異動に限らずですが、うまくいかないだけでなく、”受け身”によってネガティブになることもあります。
「公務員が人事異動に悩んだら読む本」では
- 役所における人事の仕組み、異動・昇任をどのようにとらえるべきか、人事への効果的なアピール方法、異動先での取り組み姿勢が書かれている
- 人事異動を自分なりに解釈し、今後どのようにキャリア形成をすればいいかを考えるヒントが得られる
などといった声があります。
本の中でもポイントの一つとされている「キャリア・オーナーシップ」は、キャリアを組織任せ、他人任せにするのではなく、自分のキャリアを自分らしく切り拓いていく意識を持つ必要があるよ。ということです。
これは僕も常々そう思っています。自分で選び、自分で動くことはものすごく大事だと思うんです。
ですが、できている人って意外と少なかったりしますよ。または、一度はできてもつい流されがち、ということもあると思います。
大事なことを度々思い返させてくれるこのような本一冊を持っておく、というのは良いかもしれませんね。
このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む転職の思考法
公務員が辛くなったり、新しいことがしたくなって、転職しようかと悩む人もいるかもしれません。
僕も公務員時代から、ある程度辞める計画もあったものの、辛い経験もし辞めて起業したんです。
でも、一歩踏み出せない、特に家族のことを考えてしまう、という場合もあるでしょう。
そんな時一人で抱えこむとどんどんきつくなるかもしれませんが、本などを読んで視野を広げたり、少し客観的に考えてみるというのも良いと思います。
特に公務員は、全体の人数はあまり変わらないものの30代など若い人が減っていたり、20代で転職を考えているというアンケート結果もあるんですよね。
「このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む転職の思考法」という本では、
- 若い人に良いかも
という口コミもありますよ。
ちなみに、僕個人的な意見としては、必ずしも転職=成功というわけではないと思っています。
”動くこと”は必要だとは思いますが、”どんなにリスクが高くても転職した方が良い”とは考えません。
転職するのであれば、なるべくリスクを減らした方がいい、と思っていますし、実際に僕も金銭的に困らないように準備してから辞めました。
もし、本を読む以外でも転職のヒントが欲しいという場合で、僕がどうしたのか興味があれば、プロフィールなどをみてみてくださいね。
公務員が読むのにおすすめの本は?:「調整力」、「思考力」など能力アップに関する本

公務員というと、街づくりとか、法令の整備など規模の大きいことがありますよね。
しかし、実際にやるのは地味な仕事も多いです。
そして、やってみて大変なのが「調整」という仕事だ、という人が結構います。
また、調整をはじめ、様々な仕事で必要になるのが思考力です。
公務員は法律などルールに則って仕事をしないといけないとか、単純作業が多いとか、ミスを恐れるあまりに”思考停止、キツイわ”なんていう人もいます。しかし、思考力を働かせないといけないときもたくさんあるんです。
ですから、「公務員」としても、自分にとっても、大事な能力を磨こうというわけですね。
公務員の場合、難関場合取得よりもこれらの能力アップの方が実戦で役立っていると感じられるかもしれません。
合意を生み出す!公務員の調整術 [ 定野司 ]
中には”上司を見たら、1日の90%は調整業務をしている。自分にはそれができる気がしない”、”公務員の仕事を一言で言うなら調整だ”という声もあります。
担当になれば、内部と外部の間で、とにかく調整調整…といった具合です。
調整というのは、まず○○調整課や、調整担当のように「業務としての調整」があります。
そしてそれ以外にも、国家公務員でも地方公務員でも、事務でも僕の元の仕事のように公安系の仕事でも、常に職場の内部、外部と”うまくやる”力というのがめちゃめちゃ重要です。
難しい面もあるとは思いますが、磨きたいスキルでもあります。
相手と自分の利害をはっきりさせ、いいところを取っていくスキルというのは、”民間企業へ転職するときに強みになると思う”という声もありますし、僕のように起業したとしても必要です。
本を読んでもシチュエーションは様々で「教科書通りにはいかないんよ…」ということもあるかもしれません。
しかし、多くの引き出しを作っておいて損はないな、と思いますよ。
転職エージェントに公務員の調整業務経験は評価されるって言われたけど、ぶっちゃけ外部との調整より庁内調整の方が大変だったな…
何をやるにしても敵は内部にあり。
それに比べたら対外調整のほうが楽だったよ…— トミヤマ@元公務員 (@ANA_a380) September 6, 2022
公務員のための問題解決フレームワーク
思考力と言えばロジカルシンキングが一時ブームになっていましたよね。
○○シンキングにもいろいろなものがあるのですが、仕事の上ではロジカルシンキングを含む3つの思考法(トリプルシンキング)が特に注目されています。
その3つとは
クリティカルシンキング(前提を疑う)、ラテラルシンキング(自由な発想)、ロジカルシンキング(論理的に理解する)です。
「公務員のための問題解決フレームワーク」では、そのうちラテラルシンキングとロジカルシンキングの両方を使い、自治体で起こりえる事例などと合わせて説明されています。
口コミでも
- フレームワークの本は多数出版されていますが、行政の現場で解釈して使うのは大変。この本では日常発生する事例が書かれており、同種の事例に当てはめて使うことができる。
という声がありますよ。
ちなみに、こういった思考は公務員にも役立ちますし、もし”公務員だけど副業なんかしたいんやけど”、という場合にも役立つと思います。
公務員でもできる副収入を得る方法については、別の記事でも書いています。興味があればそちらもみてみてくださいね。
僕の本の選び方

本を選ぶときに、どうやって選ぶか迷うかもしれません。
そこで、参考までに僕の本の選び方を紹介します。
僕は一気に20冊くらい買う
僕の場合は、
単語で調べて、ランキング20くらいまで一気に買います。
例えば、心理学で検索して片っ端からって感じです。
20冊読めば、人に話せるくらい詳しくなれる
僕が20冊くらい一気に買う理由は、経験上、「大体20冊読めば、そのテーマの知識が、人に話せるくらい詳しくなれる」と感じているからです。
また、いろんな視点からの解釈を読めるので知識がフラットに入ってきます。
実際に、人に話す、アウトプットすると、自分への知識の定着にも有効ですよ。
また、問題の大きさなどにもよりますが、なるべく知識などの”点”を増やした方が”線”となりやすく、自分なりの知識やアイディアとなり、役立てやすくなると思いますよ。
そして、本を読んだら解決する、と思って読むのではなく(実際に、本を読んでそれによって速攻人生が好転、とはいかないでしょう。)
- 本を読んで、自分なりにその問題や知識を理解する
- 現在の自分の状況や知識と比べてできていること、できていないことは何か、使えそうな知識や技術はあるかを明らかにする
- ”まだ足りない”と思えばそれは何かを考えて、補う
といった感じで、もっと細かく考えると、部分的にでも行かせるものが出てくることもありますよ。
ちなみに、なんとなく本を買って読んでみて「役に立たないじゃないか!失敗した!」と思うこともあるかもしれません、
しかしそれも、「自分が求めていることや問題が何なのか、よりわかった」とも捕えられます。
違う視点で学ぶのもいいですし、もしかしたら「本では足りないから、実際に人に聞いてみよう」と、本以外の知識習得や問題解決方法で自分に合うものを見つけられるかもしれません。
それでもいいわけです。大事なのは、能動的にやるということです。
ぜひ、自分のために本を読むなど、一歩、行動してみてくださいね。
まとめ
- 公務員も本を読むのがおすすめ
- 公務員におすすめ→仕事の基礎に関する本、異動などの悩みに関する本、調整力の本など能力アップにつながるもの
読んだ方が良い本というのはたくさんあります。
何より、能動的にできることをやるというのは、スキルアップや問題解決の糸口になり得ます。
ぜひ、自分の幸せに向かって一歩、進んでみてくださいね。
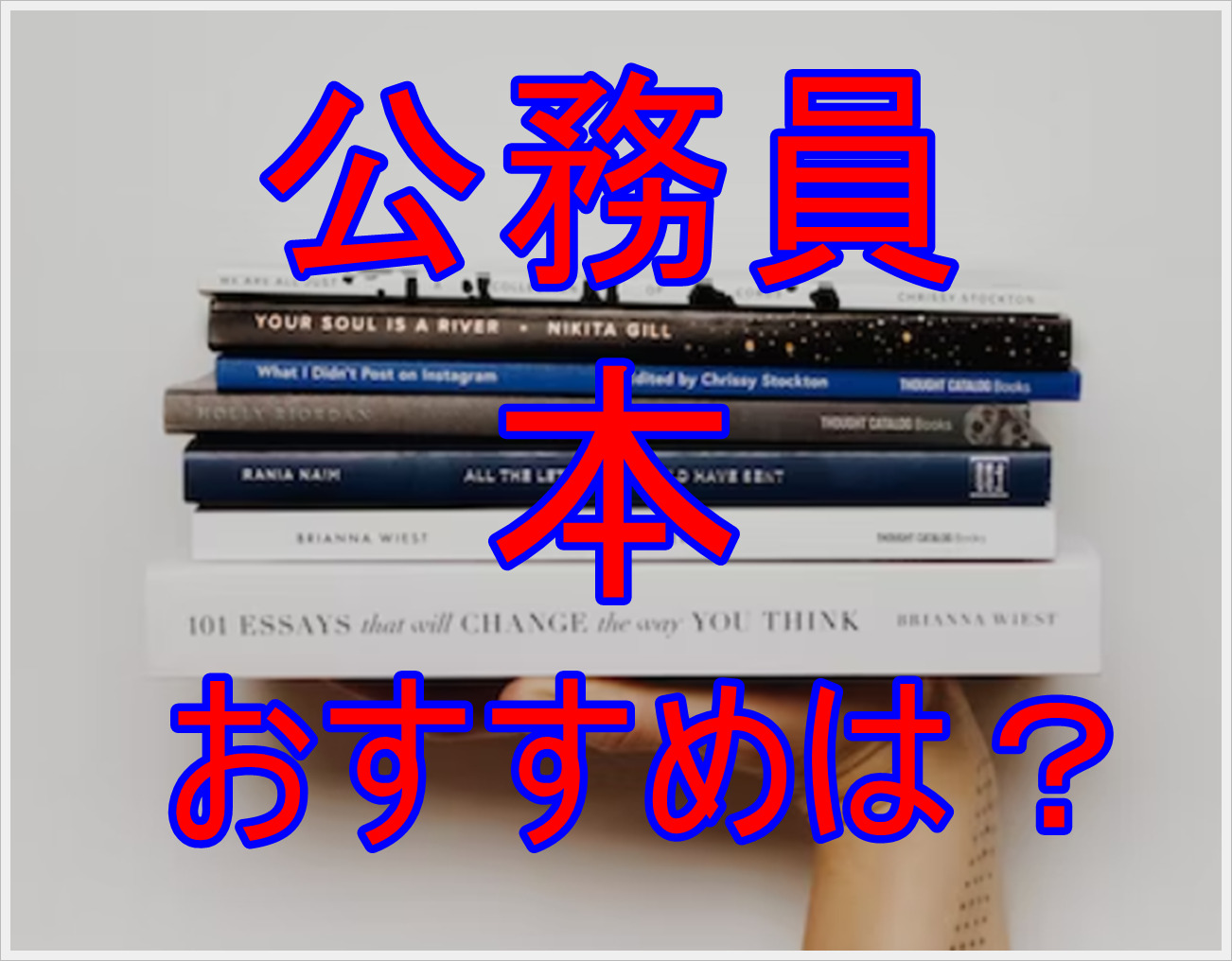



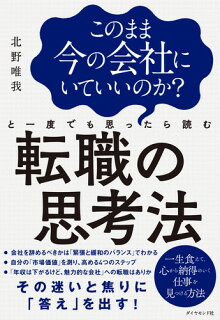



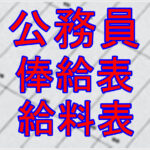


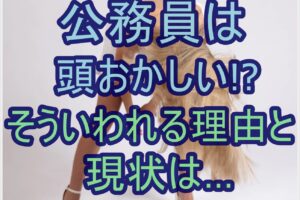



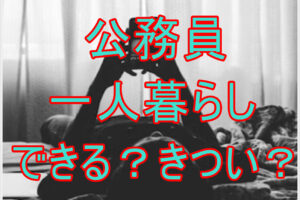
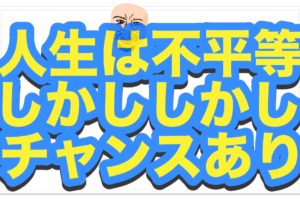
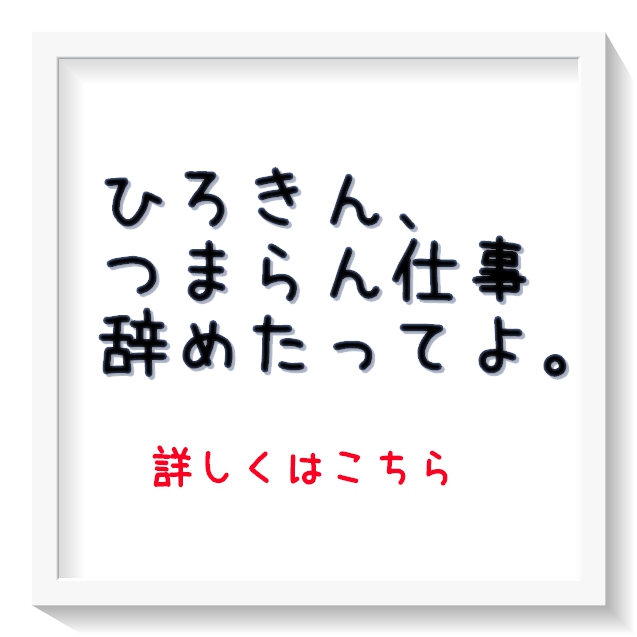




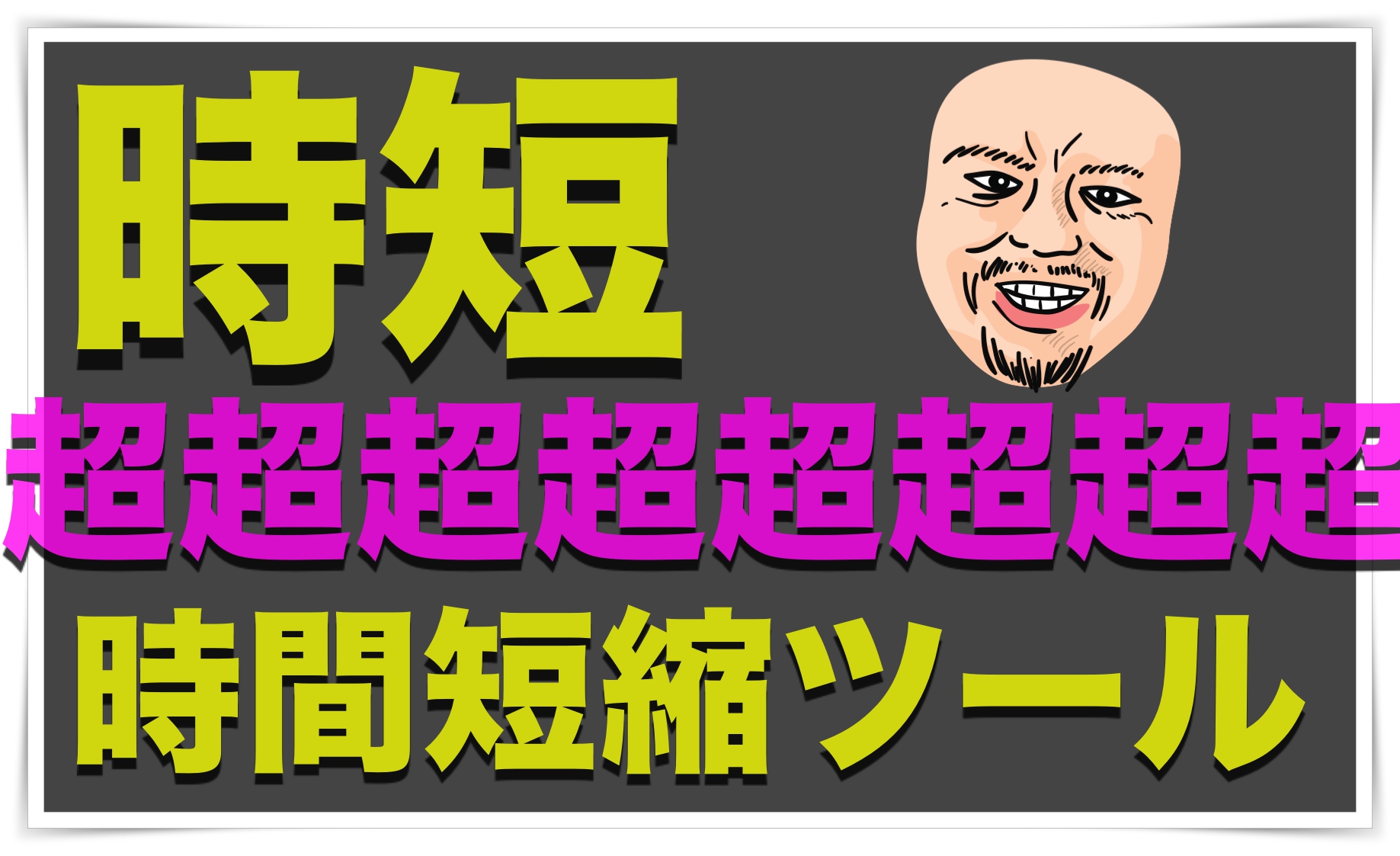


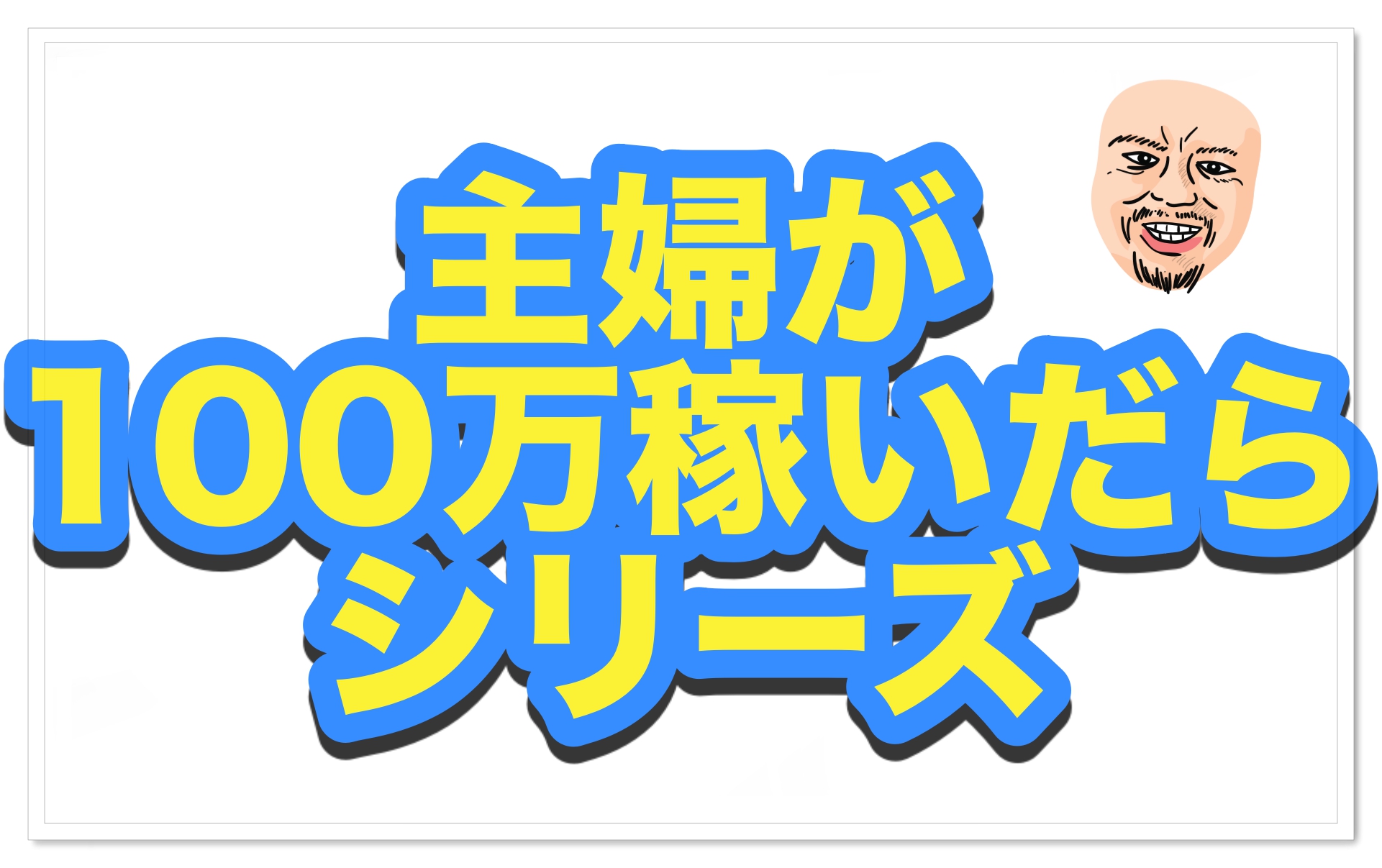
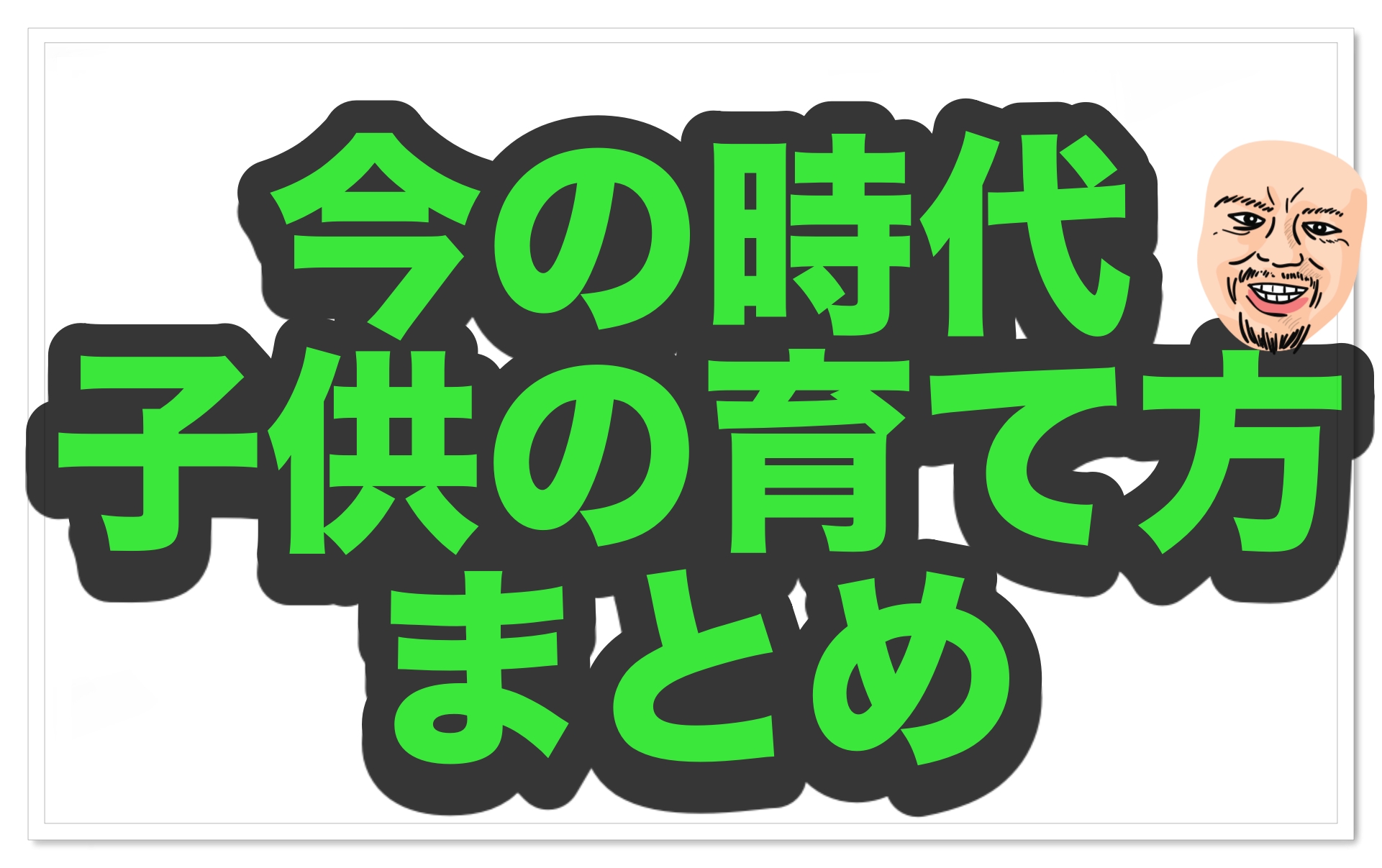

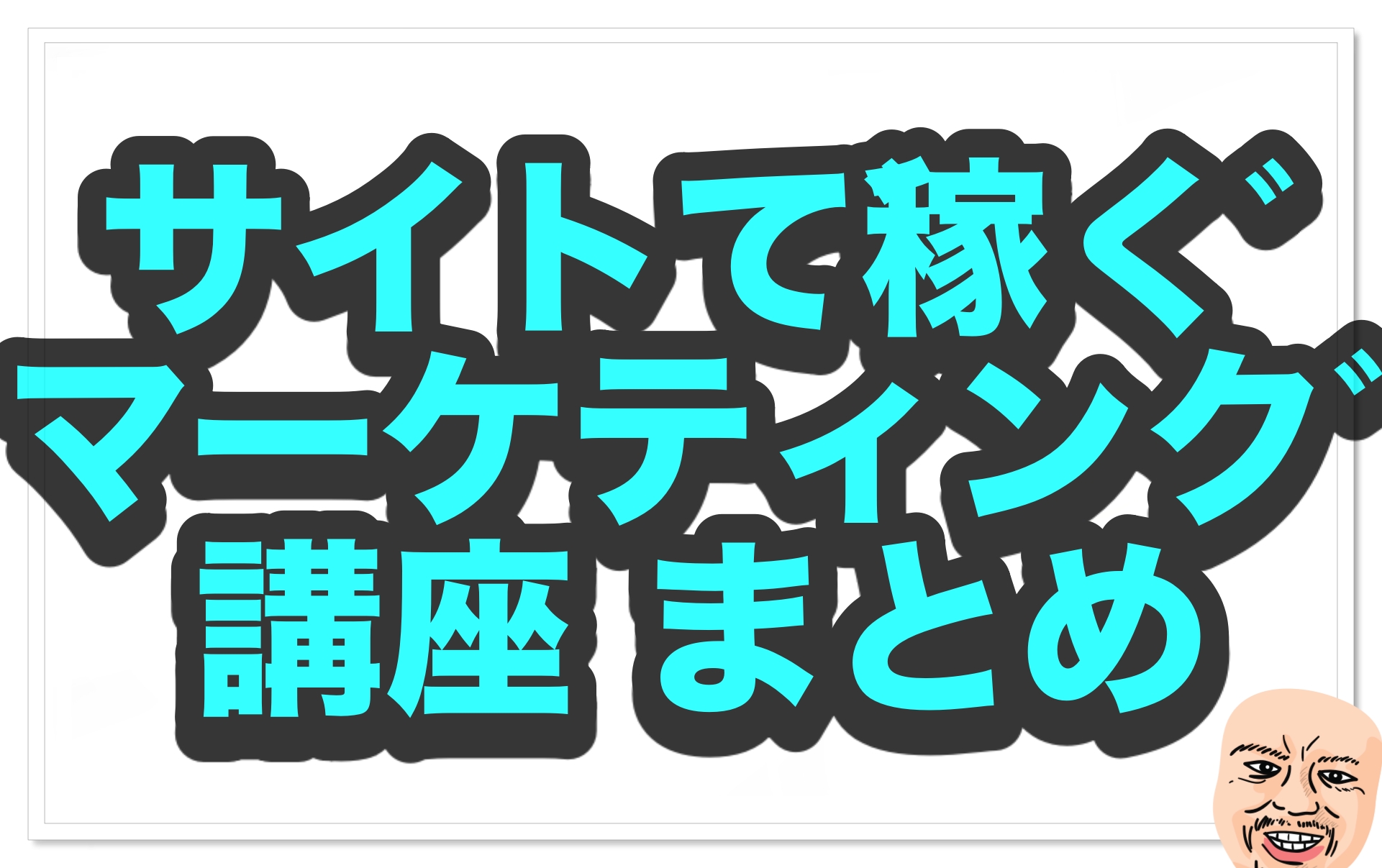

コメントを残す