まいど、ひろきんです。
今日は公務員の「note」活用についてです。
公務員だけどブログをやってみたいと思った時に、「ブログにも色々あるけどnoteってどうなんだろう?」と気になりますよね。
公務員は「note」を使えるのか?
公務員がnoteを使う時の注意点はあるか?
メリットやデメリットはある?
など、公務員のnote使用に関する疑問を調べてみたので
ぜひ参考にしてみてくださいね。
noteとは?公務員も使える?
- noteは誰でも文章や動画を投稿し、他の人との共有ができる場所
- noteの利用料は、無料もしくは機能が追加された2つの有料プランがある
- 公務員もnoteを利用できる。公務員個人/公共団体の両方に利用者がいる
- 公務員がnoteきっかけで収入を得るのは、OKな場合とNGな場合がある
公務員でもnoteは使えます。
ただし、なんでもオッケーというわけではありません。
特に、noteの特徴でもある「記事の有料化」や、「noteを使っての副業」には注意しないといけない点があります。
noteの使い方によっては、公務員の規定に反し、懲戒処分の対象にもなりかねません。
十分に気を付けてください。
noteは手軽に文章や画像、イラストなどを投稿でき、共有し合える
noteでは誰でも手軽に文章や画像、イラストなどを投稿できるプラットフォームです。
公務員でも利用することができ、公共団体も利用しています。
例えば○○市公式のように自治体公式のnoteもありますし、「△△課」や「××市教育委員会」、「□□町ふるさと納税」など、内容が絞り込まれたページもありますよ。
また、個人でも、登録すれば一定のサービスまでは無料で利用可能で、
- テキスト
- 画像
- 映像
- 音声
- つぶやき
などのコンテンツを投稿できます。
実際にnoteを見てみると、現役公務員の方で投稿をしている人もいますよ。
内容も、仕事のことから個人の考え方など様々になっています。
公務員がnoteを使うメリットは?
数あるプラットフォームから、公務員がnoteを選ぶメリットを考えてみました。
- 無料で始められる
- シンプルで使いやすい
- 無料でも広告が表示されない
さらに、将来的に転職したり起業し、ブログでの収益化を考えている場合は
- 自分の魅力アピールの場になる(ファンづくり)
- 記事を有料化できる
- 金銭的応援をする「サポート機能」がある
無料で手軽にはじめられるのがnote
公務員だと、「自分が今までブログをやったことが無いだけでなく、周りにもそんなにやっている人がいない」ということもあると思います。
そういった場合”初めてのブログで、教えてもらえる人もいないのに、いきなり有料というのはハードルが高い…”と思うこともあるのではないでしょうか。
僕も元公務員だった時思っていたのですが、公務員のお給料ってそんなに高くはないですしね。
(余裕のある人もいるとは思いますが…)
”ブログやってみたいんやけど、コストはかけたない。できれば無料ではじめられる環境がええなあ”という場合に、noteのようなサービスを利用するのも良いと思います。
無料で始められる他のサービスと比較
note以外にも無料でブログをはじめられるものがあります。
「Amebaブログ(アメブロ)」や「はてなブログ」などですね。
noteとアメブロやはてなブログを比べてみると、まずわかりやすいのが文章の装飾の違いです。
- 装飾が少なく、シンプルでカッコよくできるのがnote
- 装飾が多く、自分の好みにできるのがアメブロ、はてなブログ
ということがあります。
次に、広告です。
なんと
- noteは無料版でも広告が表示されない
- アメブロやはてなブログは無料だと広告が表示される
んです。
noteで装飾を楽しむのは難しい。しかしその分、文章が磨かれる、かも?
noteでは良くも悪くも?装飾機能がほぼなく、見出しや太字、中央寄せくらいです。
字体はユーザー設定よりゴシック体⇔明朝体を変えることはできますが、部分的に変えるということはできません。
noteは装飾を楽しめるかどうかと聞かれたら「うーん」というところかもしれませんね。
しかし装飾が少ない分、作業はとても簡単です。
また、絵文字や画像などを使って色味を入れることはできますよ。
更に、装飾に頼れない、頼らない分、”読みやすい文章”を一層意識することになり、文章作成の能力アップにはなるかもしれません。
読みやすい文章が書けるようになれば、公務員の仕事上でも役に立つと思います。
ちなみに、文章力を上げるにはアウトプットだけでなくインプットも必要でしょう。
本などを読んでみるのも勉強になると思います。
例えば、「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。という本があります。Amazonでも作家研究カテゴリで一位となっていますよ。(2023年3月8日時点)
装飾を手軽にたくさんしたいという場合は、note以外の方がいいかもしれません。
装飾をうまく使えば、個性が出せたり読みやすさのアップにもつながります。
しかし、使い方を間違えるとかえって読みにくくなったりもしますよ。
いずれにせよ研究が必要ですね。
僕の周りの文章書かれている方々で使われてる印象が多いのは、上から
・はてなブログ
・note
・アメブロの順番ですね〜
文章をしたためるだけなら断然noteがおすすめです(余計な装飾ができないので考えることが少ない)
逆に、文字色とかちょっとしたHTML編集を行いたいならはてながおすすめです
— のっぴ (@noppitter) March 7, 2023
無料でも広告が表示されないのがnote
noteは無料版でも広告が表示されないです。
一方、アメブロやはてなブログは会費600~1000円くらい払えば広告は消すことができますよ。
例)「はてなブログ Pro」2年コース:¥14,400、月額換算600円)
伝えたいことが多いのでしたらnoteもいいかもですね!
広告がついていてもOKなら無料なのがAmeba(広告非表示にすると月に1000円ちょっと支払う形)ですかねー— 大福ちゃん (@ichi5daifuku) May 29, 2022
広告が表示されても「無料で使わせてもらってるんやし…」と思うかもしれません。
しかし広告が非表示だと、ページを開いてくれた人のスマホやPCでの読み込みのスピードが速くなったり、通信料の削減になります。また、余計な情報が入らないので読者にとっては読みやすい記事になりますよね。
書く側としても、広告に飛ばれてしまい、最後まで見てもらえなかった…ということも減るかもしれません。
わざわざお金を払って非表示にする人もいる広告が、無料で非表示になっているのはnoteの魅力の一つでしょう。
(余談ですが、広告を表示しないnoteの収入源は有料コンテンツを読者が購読・利用した場合、当該コンテンツ代金から一定の料率に基づくサービス利用料がメインなんだそうです。)
初めて書く、公務員として書くなら、少し難しい内容でも読まれやすいnoteがおすすめ
初めてブログを書く場合、「なかなか読んでもらえない…」と悩み、挫折することも多いと思います。
しかし、noteを使っている人の感想を見てみると、「初心者でもnoteは比較的読んでもらいやすい」といったものがありますよ。
なぜなのか理由を考えてみましたが、
- カテゴリ別での記事紹介が目立っている
- トップページに「ランキング」のようなものの表示はnoteには無い
から、というのもあると感じます。
人気順ではなく、かつカテゴリ別で表示されているなら自分の記事も目に留まる位置に表示される可能性が高まるのではと思います。
また、カテゴリを意識すると自分のコンセプトも表現しやすく、興味がある人には継続して読んでもらえるかもしれませんね。
さらに、自分と同じような分野で投稿している人の記事が読まれれば、おすすめとして自分の記事も表示してもらえるチャンスがあります。
一方、アメブロやはてなブログでは芸能人の方のブログや、トップブロガーさんたちのランキング、人気記事ランキングなどが目立っていると感じます。
そういった中で、最初から読んでもらえるというのはなかなか難しいかもしれません。
公務員や地域、教育などの内容とも相性のnoteは相性が良い!?
公務員として書く時には、「公務員だから書ける内容」をテーマに選ぶこともあると思います。
公務員の職場のこととか、取り組んでいることなどですね。
中には得意分野として法律や税金について書いている人もいます。
(もちろん、好きなことや趣味のことを書いている人もいますよ。)
こういった内容に関しては、noteの方が読まれやすい可能性があります。
それというのも、各ブログサービスのユーザー層と、自分の書きたいものが合っているかどうか、というのも投稿を見てもらうのに重要な要素になっているからです。
投稿を見てもらうには、グーグルなどの検索で表示される以外にも、noteやアメブロなどそれぞれが利用しているプラットフォーム内で読む記事を見つけるというケースもあるんですよ。
例えばアメブロでは
- 女性(特に子持ちの主婦など)
が多く、
人気記事は
- 子育て
- ファッション
- 料理、レシピ
のことなどが上位になっています。(参照:Ameba media guide2023年1-3月期)
子育て中の女性が、子育ての記事を読んでいて、周辺に表示されたファッションの記事も気になって読む、というような流れは想像しやすいですが、そこで男性が好みそうなタイトルを見せても読んではもらいにくい、というわけですよね。
はてなブログでは
- エンジニア
が多く
興味分野は
- インターネット
- 食べ物
- ガジェット
などが上位となっています。(はてなブックマークなど、はてな全体で/参照:はてなメディアガイド2023年4-6月版)
noteでは
- 会社員
に次ぎ、
- 公務員や公共団体
などがユーザー層として多いです。
- 投稿者がそれぞれの視点で書いた記事や、知識/経験を生かした、悩み解決系の記事
も読まれています。(参照:どんなnoteが読まれた?2022年を彩るnote30選!)
ということは、少し難しい内容や行政について知っていたり、興味があったりして、比較的読んでもらいやすいのではと思います。
また、noteは教育系にも力を入れています。教育委員会などと連携し、「出前授業」をしたり、学校の情報発信のサポートもしているんですよ。
note には「note pro」という月額8万円の有料サービスがあるのですが、中央省庁や自治体には無償しているんです。
そういったことからも、「公務員としての情報発信」とも相性が良いのではと思います。
自治体広報界では知らない人がいない愛媛県内子町の広報担当兵頭さんのnote記事。来年度広報担当になる人や今広報担当で悩んでいる人は必読。
自治体広報担当のプライベートFBグループでは毎週有益情報が投稿されています。参加依頼はこちら▶︎ https://t.co/C8OSGKRFtG https://t.co/b6T5MwR2n6
— 小出 高也 | 広報の人 (@mojamidori_jp) March 6, 2023
ほぅ。
すでにnoteで発信してる福島県の自治体はあるけど、効果どのくらいなんだろうね?福島県教委が「note」に公式サイト開設 県立校紹介、学習情報発信 (福島民報) https://t.co/R8xBp4hFDg
— 山根麻衣子@ローカルライター福島県浜通りコンシェルジュ (@himawari63) March 8, 2023
僕のおすすめは、自分の得意なこと、自分にできることを発信するために、それに合った環境をえらぶこと
自分の書きたいものに合わせて投稿内容や、合うプラットフォームを選ぶのがおすすめですよ。
僕もブログや情報発信をしているのですが、ワードプレスという有料のサービスや、note、Twitterなどいろいろ併用しています。
内容も様々になっていて、使い分けている感じですね。
noteで有料記事を作った経験もあります。
節約術を書くこともあれば、公務員を退職した僕の一日のルーティンを上げたYouTubeなんかもあって、それぞれに反応があったりなかったり、嬉しいと同時に勉強になります。
ですから、公務員だからといって必ずしも地域のこととか、仕事のことを書かないといけないとかいうわけではありませんし、一つのテーマに絞らないといけないということも無いと思っています。
noteも選択肢に入れつつ、自分の目標に沿ったものを見つけてみてください。
公務員がnoteを使う時の注意点は?
公務員としてnoteを使う時に注意したい点の一つ目は
- SNS利用に関しての注意
です。
noteは簡単に情報発信ができてしまいますから、その分気を付けないといけないですね。
note利用者ではありませんが、SNSの利用が不適切で懲戒処分になった公務員もいますよ。
SNSを利用する中で、守秘義務や信用失墜行為、誤解を招く内容には注意
まず、noteに関わらず、「SNS」利用に関しての注意です。
公務員は特に「守秘義務」、「信用失墜行為」に対して注意することが必要です。
例えば
- 職務についてが公正性が疑われるような内容
- 誹謗中傷
- 差別的な発言
などとならないように、気を付けないといけません。
また、公務員であることや所属団体を明らかにしたうえで個人でSNSに投稿する場合、「自らが所属する組織の見解を示すものでない」とあらかじめ断っておくことが必要です。
ただ、十分に気を付けたつもりでも誤解されることもあるのがSNSなんですよね。
個人の見解であるとの断りをしても、組織の見解であるように思われたり、一部が切り抜かれて拡散される可能性があります。
万が一不適切な投稿や人に不快感を与えるような投稿となってしまった場合は
- 削除
の他、場合によっては
- 上司への報告
- 謝罪
が必要になることもあります。
慎重に行いましょう。
このことは、総務省の「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」や各自治体の「ソーシャルメディアの利用ガイドライン」(ネーミングやガイドラインの有無は自治体によって異なります)でも記載されています。参考にするのがおすすめですよ。
noteを利用する上での注意点。noteでの副収入はどうなのか
noteは有料記事を作成、販売できることが特徴でもあります。
公務員でも「副業としていけるんかな」ということもあるかもしれません。
まず公務員の副業ですが、基本的には”許可が無いとできない”です。
公務員が副業をやって懲戒処分されていることがありますが、内容どうこうより「無許可」というのが原因なことも多いです。
https://twitter.com/ShunBlog190/status/1481059321463308291
内容に関して公務員としての”不適切”を証明するのが難しくても、「許可取ってなかった」というのは紛れもない事実になってしまいますからね。
20万円以下の収益で確定申告不要でも、副業には当たるので自営なら許可が必要
「副業可能」と「利益が20万円以下なら確定申告不要」をごっちゃにしている人もいるかもしれません。
国家公務員法では
- 自ら営利企業を営んではいけない
- 営利企業の役員になったり報酬を得て事業、事務を行うには許可が必要
と決められています。
一方、携わる企業の規模や報酬の額は明示されていません。
つまり、「〇円以下ならオッケーやで」ということでは無いんです。利益の額に関わらず、副業することには許可が必要なんですよ。
確定申告不要かどうかはあくまでもバレにくいかどうかという話です。
確定申告不要な額しか稼がなくても副業は副業ですので、注意しましょう。
公務員ができる副業は?
最近ではだいぶ制限や許可基準が緩和されているようです。
ただ実際には、「公務員として適当でないと認められる場合」は許可が下りないこともあります。
そのため、
- 地域貢献
- 農家やお寺など家業
- 講師
などでないと難しいでしょう。
- 作家
に関しては、表現の自由もありますし、趣味の範囲として認められることもあります。
ただ、報酬を得る場合は許可が必要ですし、本などの場合は内容も情報漏洩などにならないよう十分に気を付ける必要があります。
以前、副業について、自分の勤務する自治体に確認をとった。
現状、どこかの団体から申請があったなら別だが、個人で何かをやるものに許可は下りないとのことまだ、収入を得るものは地域貢献活動しか許可されない。
— 公務員の働き方改革のために動く人 (@civilservant22) March 6, 2023
逆に言うと、地域貢献や作家などであれば前例があり許可が下りる可能性が高まります。
noteでも作家として執筆活動ができますから、許可が下りれば有料で作品を出すことも可能かもしれません。
ただ、
許可が下りるかは所属団体(許可権者)によっても異なる
ということがありますので、自分の職場への要確認が必要です。
ちなみにnoteで公務員関係の有料記事を見てみると、
- 国会議員秘書
というケースもあります。
議員の秘書の方は「国会議員の秘書の給与等に関する法律」により、公務員として原則は副業できないものの、国会議員が許可を出せば兼職できるとなっています。
そのほかは
- 公務員を辞めて書いている
- 公務員の家族が書いている
などというケースが多いですね。
「ネットで○○なら収入を得られるって見たからやってみよ」というので始めずに、必ず職場で確認を取ったり、許可をもらって始めてみてくださいね。
僕がおすすめするとしたら、自己表現の場として使い、noteでファンを増やすこと
公務員がnote上で副収入を得るというのはハードルが高いかもしれません。
ただ、知識や経験、自分が地域貢献できることや作品などを発信すれば、そこから副収入につながる可能性はあるかもしれません。
僕はビジネスをする上ではコアなファンづくりが大事だと考えています。
そして、実体験からも、コアなファンを作るときには頑張っている過程や等身大の自分を見せるのが大切だと感じているんです。
ですから、もし将来的にビジネスをしたいと思っているのなら、いきなり商品などを紹介して買ってもらおうとするのではなく、今のうちにnoteのような場で自分を表現し、この人面白いな、と思ってもらうというのも良いのではないでしょうか。
例えばnoteで官僚への興味をもってもらおうと魅力や課題について書いていた方が、出版社からの声かけがあり、本を出されています。
【なんと書籍化します!】霞が関の人になってみた〜知られざる国家公務員の世界〜|霞いちか@霞が関の国家公務員 @ICHIKA67391911 #note https://t.co/uNp9TXJDUG pic.twitter.com/4SolqEjqWK
— 霞いちか (@ICHIKA67391911) January 26, 2023
この方はnoteがきっかけで本の発売とはなったのですが、noteの記事で魅力を感じた出版社の方が声をかけたわけで、「noteで記事を販売し収入を得ていたわけではない」んですよね。
他にも、自分の副業や販売しているものをnoteの中で紹介している方がいます。
Kindleで本を出していて、内容をnoteで紹介しているという方もいますよ。
本の内容は勉強法についてなどで、出版についても許可申請済みと明記されていますね。
また、noteの中で、「地方公務員だけど商品を作って売っています」という方や、農業を副業としてやっていることを紹介、投稿をされている方がいます。
こちらの方は、地域貢献としての商品販売で職場の承認を得て行われています。
地域貢献のために行って、利益はその活動の費用になるという場合は許可もおりやすいかもしれません。公務員がクラウドファンディングする場合などでも同じですね。
自分の収入にはならないですが、やりがいを求める場合や地域にとって必要だと考える場合は挑戦の価値があるでしょう。
農家を副業としてやっていることをnote中で紹介されている方の投稿には、「公務員の方の副業の参考になれば」ということが書かれています。
公務員で副業したいとか、農業したいと思っている人も多いと思いますから、こういった投稿は勉強になりますよね。
投稿者の方々にそういった考えがあるかどうかは別として、noteや取り組みを通して実際にやり取りができたら、ファンになってもらえるということがあると思うんですよね。そうなると、もし別のことをやろうとしたときにも応援してくれる可能性がある、というわけです。
いずれにせよ職場には確認、許可を忘れずに、ルール違反せずに行ってくださいね。
まとめ
- noteは公務員でも文章や動画を投稿し、他の人との共有ができる場所
- noteの利用料は、無料もしくは機能が追加された2つの有料プランがある。装飾は最低限だが無料でも広告が無いく
- 公務員個人/公共団体の両方に利用者がいて、noteは教育関連に力を入れてもいるため、公務員として記事を書くにも馴染みやすい
- 公務員がnoteきっかけで収入を得るのは、OKな場合とNGな場合がある
公務員もブログをやっている人は多くいます。
公務員としての情報発信だったり、個人の情報発信の場として使うことで文章力を鍛えられたり、人脈も広げられる可能性があります。
一方、副業は許可基準が緩和される傾向にあるものの、地方貢献や農業でやっと、というところのため、公務員のうちはブログで副収入を得るというのはハードルが高いかもしれません。
ただ、今後規制がさらに緩和される可能性はありますし、収入を得なくても職場以外の場所で活動することや身に着けた思考やスキルは無駄にならないと思います。
特に、能動的に何かを選びやってみるというのはとても大事で、自分の糧になると思いますよ。
ぜひ、自分の将来の目標に向かって、挑戦してみてくださいね。
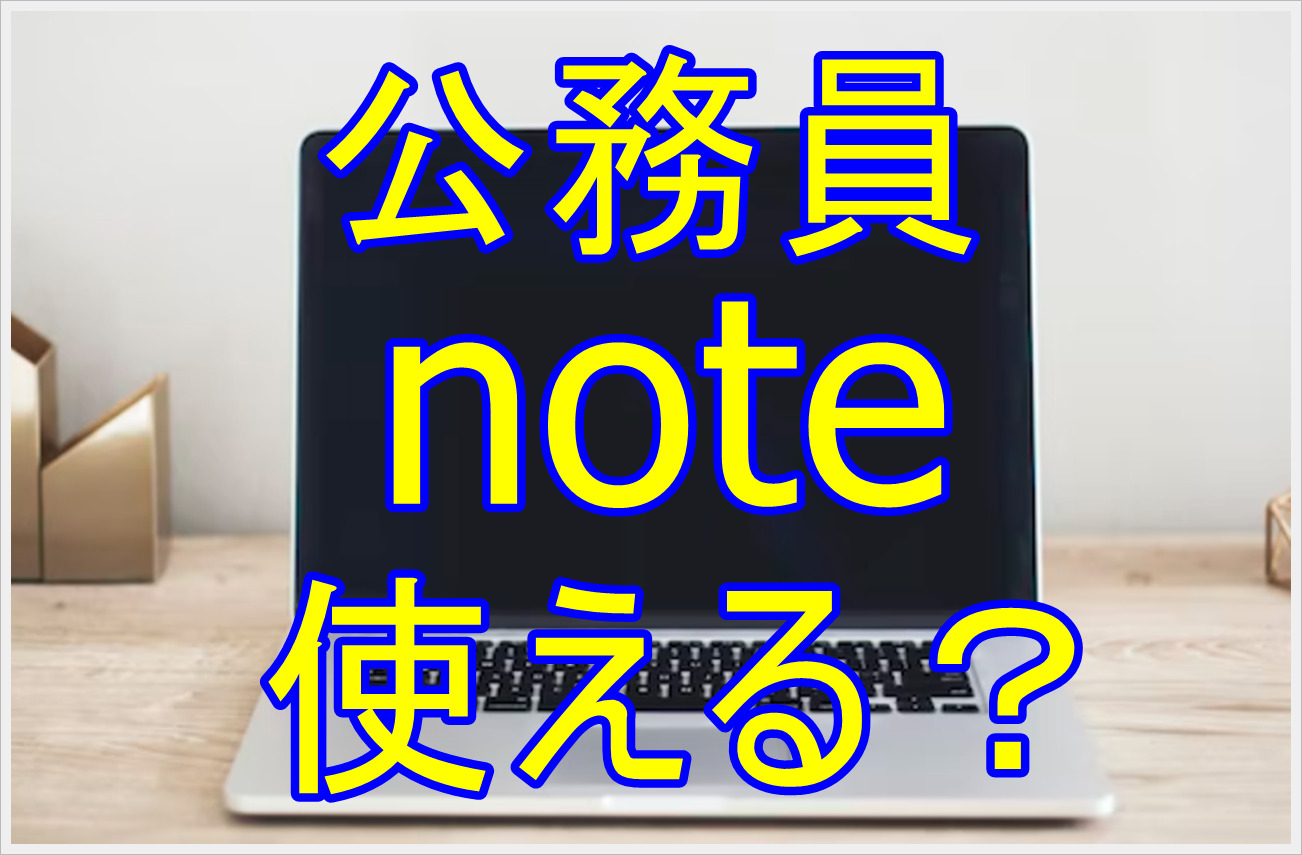


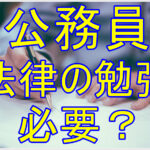





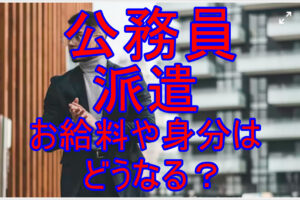



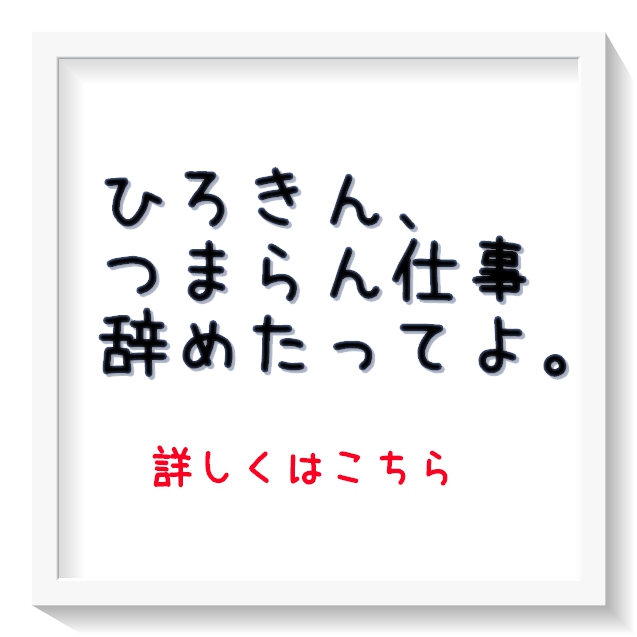




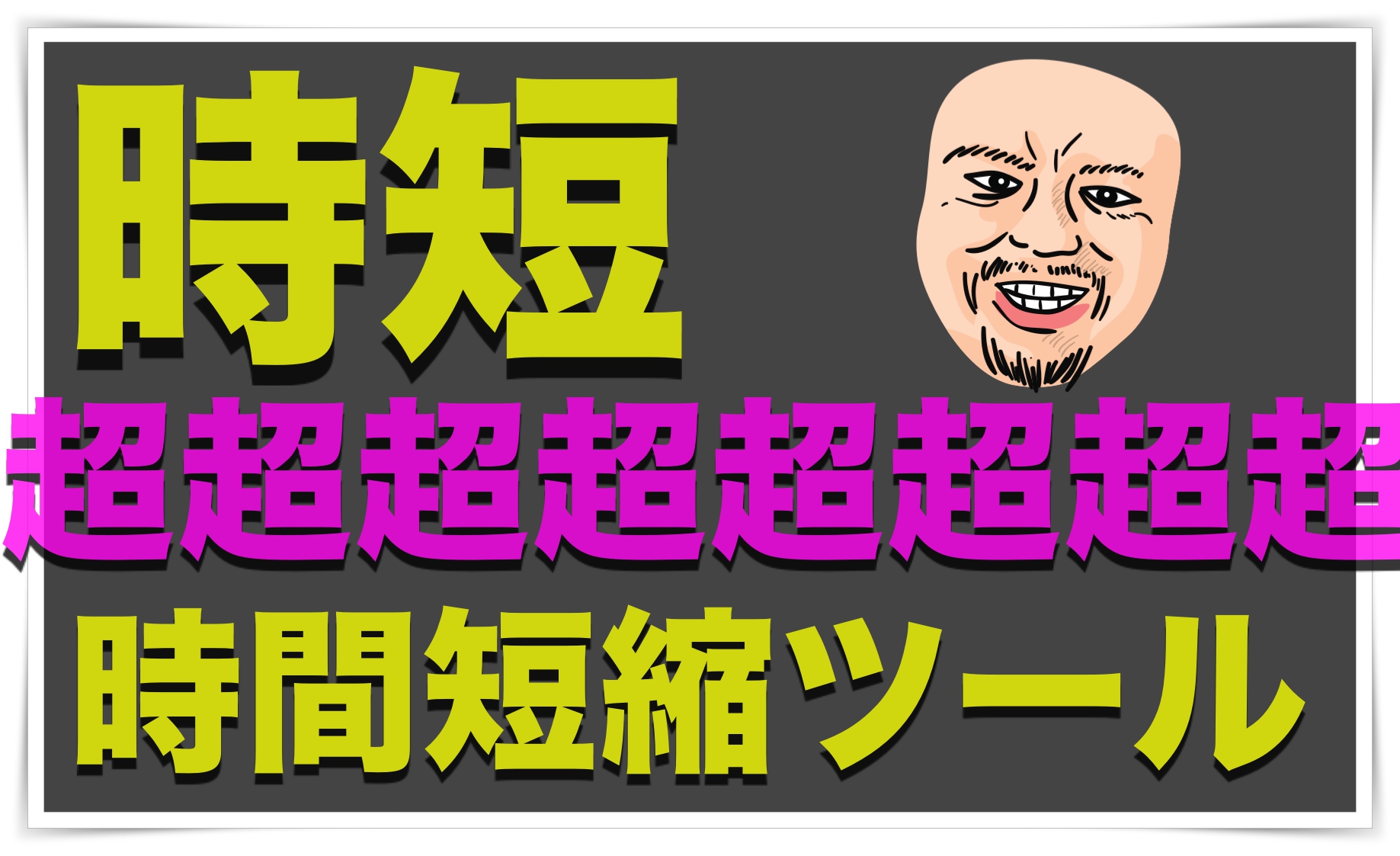


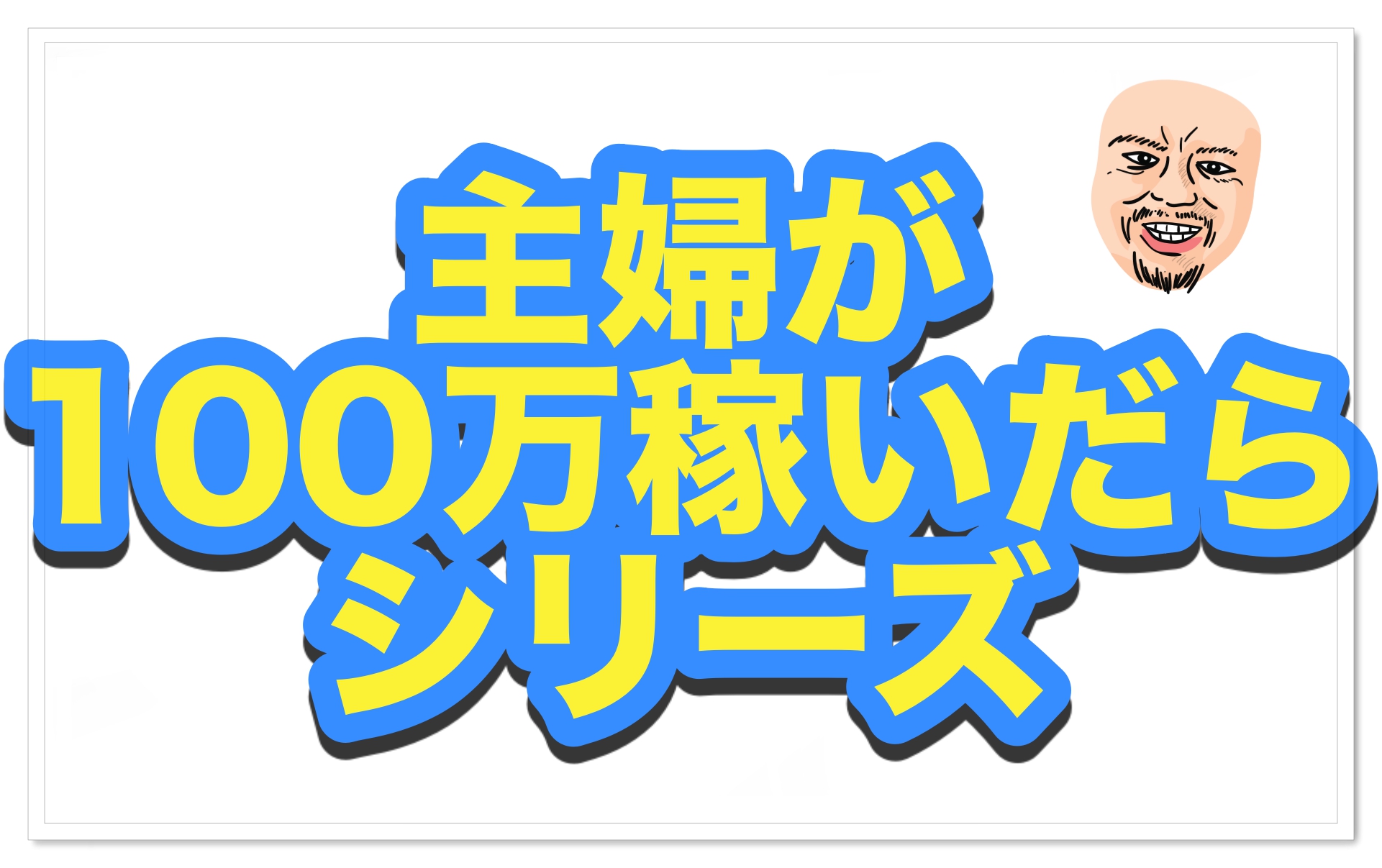
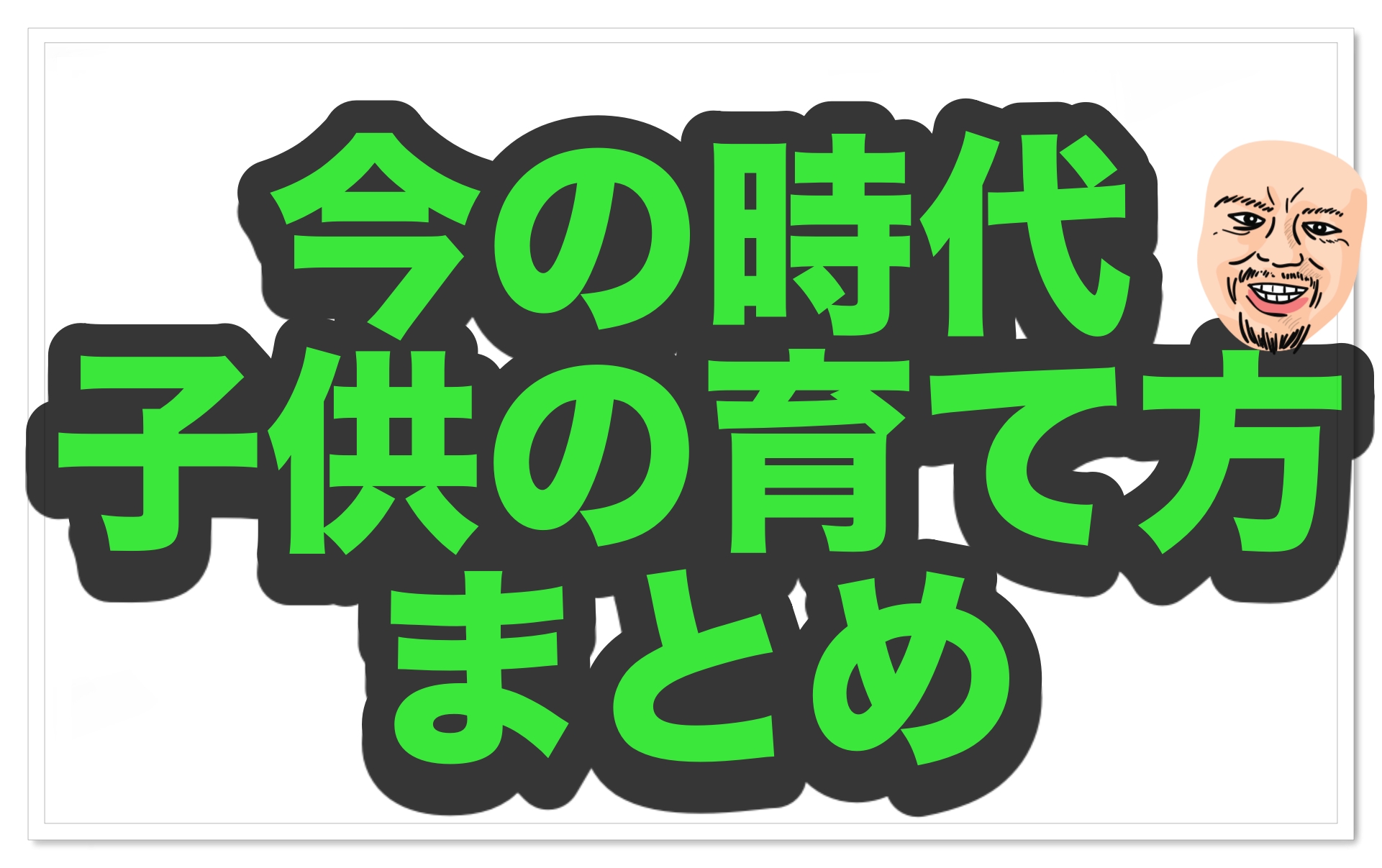

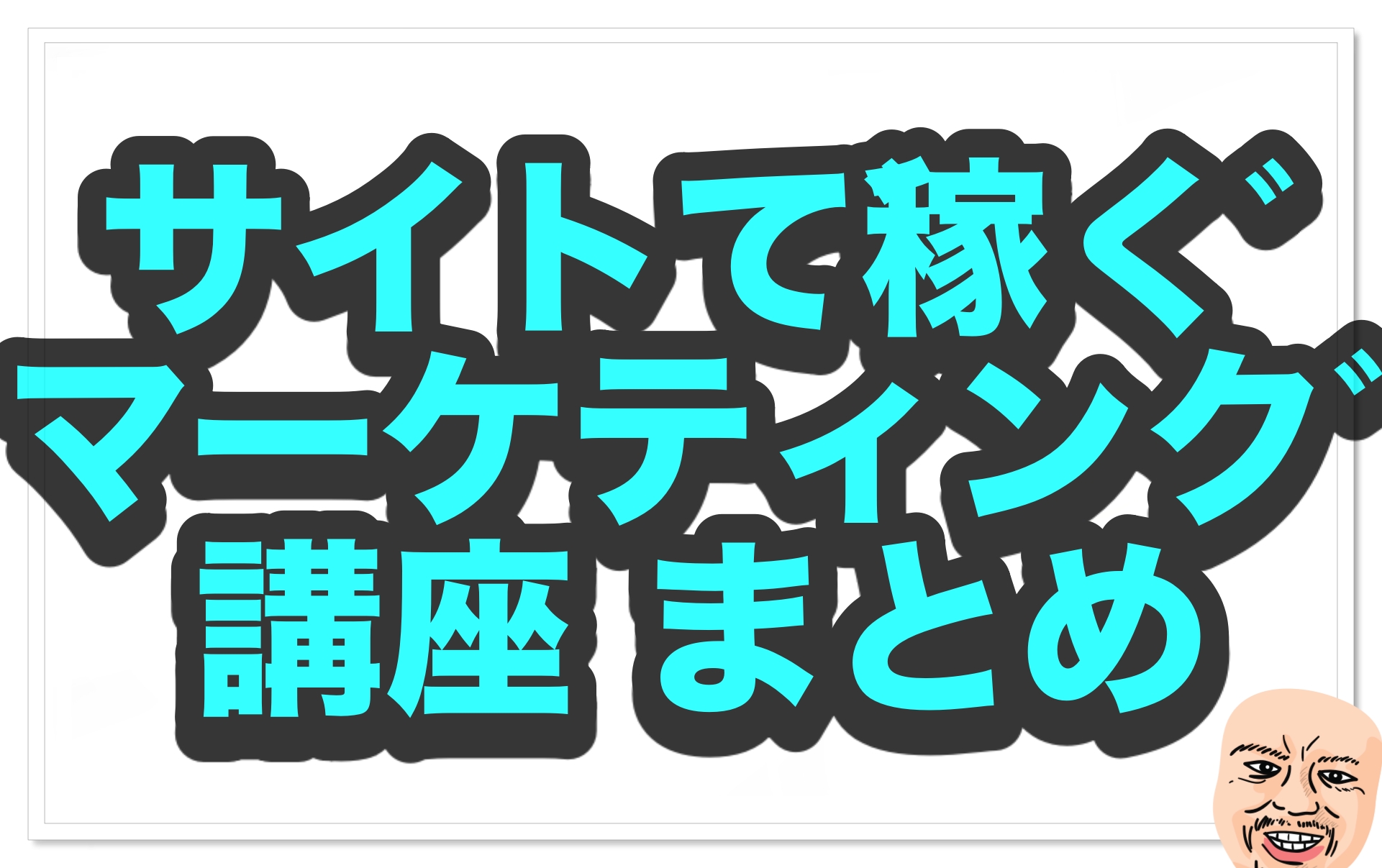

コメントを残す